
生きることが下手です。死んだふりは上手です。
役者を志していたものの、気がつくと“死体役”ばかりを演じるようになっていた吉田広志(奥野瑛太)。開いたスケジュール帳はさまざまな方法で“死ぬ予定”でいっぱいだ。「厳密にリアリティを追求するなら……」と演じることへの強いこだわりを持つ彼だが、効率を重視する撮影現場では、あくまで物言わぬ“死体”であることを求められる。劇団を主宰していた頃の後輩俳優は要領よくテレビで活躍を果たしているが、彼にはそれができない。死体役には死体役のリアルが彼の中にはあるのだ。ひとりのときでも発泡酒を口にすれば“毒死のシーン”を、浴槽に浸かれば“溺死のシーン”を演じ、常に死に方を探求する日々を送っていた。
そんな〈死体の人〉が、人生を変えられるような運命的な出会いを果たす。ある日、自宅に招いたデリヘル嬢・加奈(唐田えりか)との情事の後、彼は「ベタな質問で恐縮なんだけど……何でいまの仕事をしてるの?」と彼女に問いかける。それはそのまま〈死体の人〉にも跳ね返ってくる質問だった。「けっこう喜んでもらえるし、こんなことくらいでしか人を喜ばせられないから」と答える加奈に対して、「俺なんか誰も喜ばせられないよ……」と自嘲気味に〈死体の人〉は続ける。明るく振る舞う加奈だが、彼女もまた自身の人生に問題を抱えていた。
しかし、ある日唐突に〈死体の人〉の元に、母(烏丸せつこ)が入院するという報せが父(きたろう)から入る。気丈に振る舞う母だが、どうにも病状は良くないらしい。さらにそこに、新たな問題が発生。偶然見つけた妊娠検査薬を何気なく自分で試してみたところ、何と陽性反応が出たのだ。これはいったいどういうことなのだろうか……?
消えゆく命、そして、新たに生まれてくるかもしれない命──。〈死体の人〉こと役者・吉田広志は、一世一代の大芝居に打って出る。




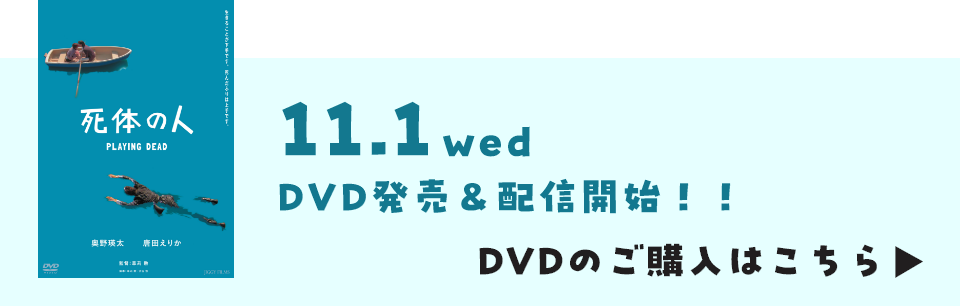






























![奥野 瑛太 as 吉田広志 [死体の人]](img/imgp01.jpg)




![烏丸せつこ as 吉田広志 [死体の人] の母](img/imgp06.jpg)
![きたろう as 吉田広志 [死体の人] の父](img/imgp07.jpg)

「死体の人」が逆手をとっての大芝居あり。奇想に発しながら、堂々たるヒューマン・シネマ。 最後に、「死体の人」が「死体」に極まるのである。
この国の長すぎる青春の苦悩をリアルにしかもオーソドックスな手法で捉えた 監督の技量は確かだ。役者も十分に応えている。 三年わたり「死に体」で過ごすことを余儀なくされた若者たちに、新たな一歩 を踏み出す力を与えるだろう。
軽さと重さ。可笑しさと哀しさ。生と死。虚構と現実。この世の矛盾を軽々と包んでしまう素敵な映画でした。
今の時代が忘れかけているささやかな感情かもしれない。
滑稽さとシリアスをジェットコースターみたいに行き来しながらこの映画が示す優しくも意外な結末に泣いた。